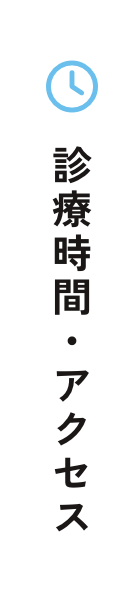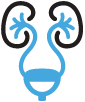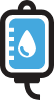腎臓内科
検尿の異常を指摘されたら、
早めの受診を。
腎臓内科・透析専門医が、
腎臓病の予防と治療から、合併症の管理、
透析まで包括的な医療を提供します。
健康診断などでの検尿異常
(尿潜血・尿蛋白など)、腎機能障害(クレアチニンが高い、eGFRが低い)を指摘された方、
身体が浮腫むなどの症状を
認める方は、お気軽にご相談ください。

こんな症状がある方はご相談ください
よく診る疾患例
慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)
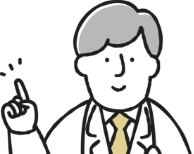
花田先生のワンポイント解説
慢性腎臓病とは、おしっこに蛋白などが漏れ出たり、腎臓の働きが健康な人の60%以下になるなど何らかの腎障害が3か月以上続く病気のことをいいます。これまで日本には1330万人、成人の8人に1人がCKDに該当すると言われていましたが、最新の報告では日本のCKD患者数は約2000万人、20歳以上の5人に1人がCKDに該当すると言われるなど、新たな国民病として問題となっています。
CKDは進行すると人工透析や腎移植が必要になるだけでなく、比較的軽度であっても心臓病や脳卒中などの発症や死亡のリスクとなると言われています。そのため、症状の乏しい早期からの介入や指導することが重要であり、まさにかかりつけ医こそがCKD診療の主役であると考えます。
CKDは難しい、治りにくい病気という印象をお持ちかもしれませんが、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン阻害薬(RAS阻害薬)(ARBとACE阻害剤)やSGLT-2阻害薬といった腎保護効果のある薬剤が使用できるようになり、適切な治療をおこなうことで、その進行を相当に抑えることが可能となってきました。
当院では腎臓専門医に加え、看護師、臨床工学技士よる集学的腎不全管理により検尿異常から末期腎不全だけでなく、脳卒中・心筋梗塞などの心血管疾患を予防することに務めます。
糖尿病関連腎臓病(Diabetic kidney Disease:DKD)
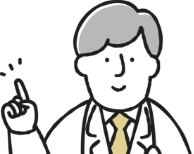
花田先生のワンポイント解説
DKDは慢性腎臓病のなかの最大かつ最重要な疾患であり、現在の透析患者の原疾患の約40%を占めます。糖尿病が10年以上続くと腎臓が傷み、尿の中に普段は出てくることのないアルブミン(血液の中にある蛋白質の主成分)が漏れ出して、アルブミン尿となります。はじめはアルブミンの濃度がごく低く、微量アルブミン尿と呼ばれ、一般的な尿定性検査では(-)~(±)となるため、尿アルブミン定量という特殊な検査でより詳しく行います。微量アルブミン尿の状態で数年間放置していると、漏れだすアルブミン尿の量が増えて、顕性アルブミン尿となり、通常の尿検査でも検査を行うことが可能となります。また蛋白尿が大量に出始める時期には、腎機能も低下してきて、血清クレアチニンが高くなります。重要なのは、微量アルブミン尿を呈する早期の時期にいくつかの治療を組み合わせて、微量アルブミン尿を正常なところまで減らすことです。
近年、SGLT2阻害薬や非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)というお薬を使用することで、透析までの期間が延長すると報告されております。
検尿異常(尿潜血または/かつ尿蛋白を指摘された)
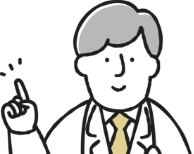
花田先生のワンポイント解説
健康診断などで蛋白尿や尿潜血を指摘されたら、原因を見極めるためにもお気軽にご相談ください。
《蛋白尿》
尿の中に蛋白がもれ出ている状態を指します。腎機能の低下や腎臓の病気を発見する大切なサインになります。主な要因は、急性や慢性の腎炎など腎臓特有の疾患と、糖尿病や膠原病、高血圧などの全身疾患があげられます。治療方法は原因により変わるため、きちんとした診断が必要となります。
《尿潜血》
尿に血液中の成分(赤血球)がもれ出ている状態(尿の色が赤くなくても、血尿の場合があります。)で、腎臓や尿管、膀胱、尿道といった尿路に異常が起こっている可能性があります。尿潜血は疲労などで一時的に生じることもありますが、腎疾患がある場合、進行して障害された機能を回復できないことも多いため、腎機能低下を防ぐためにも早期発見が重要です。
腎機能低下(血液検査でクレアチニン値やeGFRの異常を指摘された)
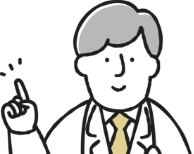
花田先生のワンポイント解説
腎臓の働きの低下を判断する項目としてクレアチニンやeGFRがあります。
《クレアチニン》
筋肉に含まれるたんぱく質の老廃物で、血液中のクレアチニンは腎臓でろ過されて尿として排泄されますので、正常な状態では血液中のクレアチニンは一定量に保たれています。ところが腎臓の働きが低下すると、血液からクレアチニンを除去することができずに血液中のクレアチニン量は増えてしまいます。
《eGFR(Glomerular Filtration Rate:糸球体濾過量)》
血液検査で現時点でどのくらいの腎機能が残っているかを示す値です。100点満点で60点以下だと腎機能の低下の疑いがあり、慢性腎臓病と定義し、精査が必要となります。
まず、どのように推移してきたか、低下してきた原因は何か、今のからだの状態などを評価します。そこから、これからどのように推移していくのかを推察します。
そのうえで適切な治療を考えていきます。食事、嗜好、運動、仕事などを含めた生活習慣を考えさらに血液検査・尿検査・腹部エコーなどで総合的に判断し、お薬の必要性についても考えていきます。
足の浮腫みなど腎臓病が疑われる症状
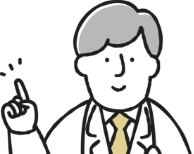
花田先生のワンポイント解説
むくみの原因は、ネフローゼ症候群などの腎臓病だけでなく、心臓病や肝臓病、甲状腺疾患、薬剤性など多岐にわたります。腎臓病に関する知識だけでなく、総合内科的な幅広い知識が必要になります。
検尿や血液検査で腎生検が必要と思われる疾患(慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、間質性腎炎、原因不明のなど腎障害など)には浜田医療センターや島根大学附属病院などと連携して、診療に当たります。健康診断で尿潜血や尿蛋白を指摘された方、下肢などにむくみを自覚している患者様は一度ご相談ください。
常染色体優性多発嚢胞腎(人間ドックや健診の腹部超音波検査などで腎嚢胞を指摘された)
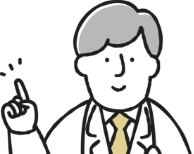
花田先生のワンポイント解説
腎臓に液体が貯留した袋状のものができる病気を腎嚢胞(腎嚢胞)と言います。健診や人間ドックのエコーやCT検査で偶然発見されることが多く、原因はよくわかっていませんが、年齢とともに多くの人に発生します。治療は不要で、年に1~2回、エコーで経過観察する程度で構いません。
だだし、両側の腎臓に5個以上の嚢胞が認められる場合、常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)といわれる、遺伝性の疾患の可能性もあります。
多発性嚢胞腎とは、腎臓に嚢胞(体液の溜まった袋)が多数存在し、左右の腎臓が大きくなる遺伝性の疾患です。さらに腎臓以外では脳動脈瘤や心臓弁膜症、大腸憩室などを合併することが知られています。多発性嚢胞腎の約半数が70歳までに末期腎不全に至り、透析が必要となることが知られています。
2014年3月にトルバプタン(商品名:サムスカ®️)による治療が日本で保険適応となり、その後も同薬による嚢胞拡大の抑制などの報告がなされております。
当院では登録医(専門医)が診療に当たり、医療助成制度の登録、必要に応じて浜田医療センターなどへの高次医療機関への紹介を行います。多発性嚢胞腎と診断された患者様、健康診断で嚢胞腎を指摘された患者様は相談ください。
腎代替療法の療法選択(そろそろ透析が必要と言われた)
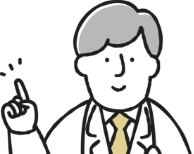
花田先生のワンポイント解説
腎臓の働きが10%以下にまで低下すると、自分の腎臓では自分のからだを浄化しきれなくなり、老廃物が蓄積して倦怠感、食欲低下、悪心、嘔吐、頭痛などの尿毒症状が出現したり、体液のバランスがとれなくなり、心不全や肺水腫を起こし、息切れや呼吸苦が出現しやすくなります。放っておけば命に関わります。そのため、腎臓の代わりに老廃物や余分な水分を除去し、不足している物質を補う腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)が必要となります。
そろそろ透析が必要と言われたら、「本当に透析が必要なのか?」「そもそも、透析とはどういったことをするのか?」「お金のことが心配」「週3回の通院はどうしたらよいのか」など、様々な疑問が頭をかけめぐることと思います。
腎代替療法の選択時はご自身の生活環境、ライフスタイルに最も適した治療法を選択することにより、より快適な生活を送っていただきたいと思っております。
腎移植を希望される患者様については、島根大学医学部附属病院や広島大学病院へ生体腎移植や先行的腎移植目的での紹介実績もあります。
検査結果をもとに、
病気の早期発見や治療方針の提示など
丁寧に行うように心掛けておりますので、
どんなことでもお気軽にご相談ください。
ご予約・お問い合わせはこちら
透析室直通
0855-52-0158- 受付時間
- 8:30-12:00 / 15:00-18:00(木曜日・土曜日8:30-12:00)
- 休診日
- 木曜午後・土曜日午後、日曜日、祝日